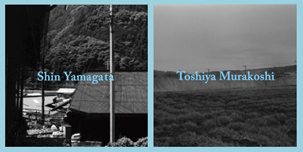「風景と写真をめぐる今日的状況について」増田玲(東京国立近代美術館主任研究員)

外界に対して、人はつねに「風景」を見ているわけではない。あらためて外界、つまり私たちをとりまく環境を風景としてとらえるには、距離をとることが必要だ。見るものと見られるもののあいだを切り離し、主体と客体を切り出すという作業をへて、はじめて風景は立ち現れる。こうした作業に、写真というメディアはとてもなじみがいい。主体である撮り手と客体となる被写体のあいだに置かれたカメラは、主体と客体を切り離し、距離をとるという構図を、ほとんど無条件に成立させる。
カメラを媒介に切り出された「風景」は、それだけですでにひとつのイメージとして成立しているが、そこではまだ、未分化な外界に対して、とりあえずの距離を確保し、ひとつの「見え」が固定されているに過ぎない。それを表象として他者に差し出すには、まだ何かものたりない。写真家が表象行為として風景をめぐるイメージを成立させるには、距離の取り方や視点の設定において、意識的にせよ無意識的にせよ、何らかの選択がなされる必要がある。そこでとりうる選択肢には、歴史的にみて、いくつかの基本的な方向性があったと考えられる。
まずは景観そのものの見事さ、美しさをイメージとして定着させ、その純度を高めていく方法。次に風景を分析、探査の対象とし、読み解くべきテクストとしてとらえ、新たな視点や知見を提示する方法。そしていまひとつは、切り出された風景をひとつの器として、そこに内面の思いや感情を仮託する方法だ。
第一の方向性としてはアンセル・アダムズの仕事にその完成型を見ることができる。ヨセミテ渓谷をめぐる一連の作品に代表されるアンセルの仕事は、いわゆる「風景写真」の典型である。第二の方向性は、ルイス・ボルツやロバート・アダムズら「ニュー・トポグラフィクス」の写真家を典型とする。彼らは雄大な自然を好んだアンセルとは対照的に、とりたてて美的とも思えない造成地などの無個性な人為的光景にこそ、レンズを向けて分析し、読み解くべき何かがあると考えた。あるいは写真家本人の意図がどこまでの射程を持っていたかは別にして、ウジェーヌ・アッジェの残した膨大なパリの都市風景写真は、第三者にとってさまざまな読解が可能な、重層的なテクストと位置づけられるだろう。第三の方向性としては、たとえばアルフレッド・スティーグリッツに始まる、「イクィヴァレント(=等価)」の美学が挙げられる。彼らは被写体と内面のあいだにメタフォリカルな関係性を仮構し、風景の描写を詩的なメタファーとして、精神性を象徴的に表象することを試みた。
もちろん、以上はとてもおおざっぱな分類であり、実際には、たとえば雄大な自然景観を称揚するアンセル・アダムズのヨセミテ渓谷の写真を、地誌的・文化史な視点から読み解くことも可能だし、同様に自然景観の描写を通じたアンセル自身の精神性の表象としてとらえることも可能である。つまり、景観それ自体を美的なものとして描出するか、分析や読解の対象とするか、あるいは内面を仮託する器とするか、これらは決然と分類できるわけではなく、ひとつの写真イメージのなかに複層するそれぞれの要素が、それぞれのバランスをとって現れていると考えるほうがいいだろう。
さらにもうひとつ、風景と写真のかかわりを考える上ではずせないのは、外界の側に力点を置くにしろ、内面の側を重視するにしろ、それらが定着されるイメージは、外界と内面の接する界面に結ばれているという点である。そこには人間の視覚を相対化する機械の眼としての写真の性質が大きく作用することになる。そうした「写真の眼」の独自性として典型的なのは、1920-30年代のヨーロッパの前衛的な写真表現に見られる、極端な俯瞰や仰角の構図など、三次元空間を二次元化する際に現われるトリッキーな視覚効果である。もちろんそこまで極端でなくとも、写真イメージは、たとえわずかなものであれ、私たちの日常的な視覚に対して、問いを投げかける違和感をつねに内包している。再びアンセルに立ち戻れば、彼は、ゾーンシステムというきわめて洗練されたプリント手法によって、写真という界面における違和感を、美的体験へと転化させたのである。
ここまで駆け足で確認してきたのは、いわば風景と写真について考えるための、とりあえずの枠組みのようなものだ。しかし風景に対して分析や読解を試みるにしても、被写体としての風景と内面のあいだにメタフォリカルな関係性を仮構するにしても、あるいは、外界と内面の接する界面としてのイメージそのものが発する問いに向かうにしても、写真家たちの仕事はそれほど単純には為されていない。そこでは同時にさまざまな問題系が参照されているからである。

たとえば今回の出品作家の一人、吉村朗は、外界と内面の接する場としての「風景」に、記憶や歴史という問題系を交錯させる。彼の「まなざし」が見出すのは、判読しがたいほどに複層するテクストの刻みつけられた「風景」である。吉村を一方の極とするならば、湊雅博の仕事はもう一方の極として対置されるだろう。湊は、吉村が写真という界面に招致したような問題系を一切捨象し、風景を成立させるために不可欠なはずの距離すらもミニマルに切り詰めた果てに、それでもなお「風景」が出現しうるかどうかを見届けようとする。この二つの極のあいだに、それぞれの写真家が、それぞれに設定した問題系を参照しながら立ち上がらせた「風景」が布置される。とりあえず今回の展覧会の成り立ちをそのようにとらえてみたい。
個々の写真家が参照する問題系は多様であり、そこに立ち上がる「風景」もまた多様である。私たちはそれぞれの問題系のありかを注意深く見極めることを求められている。今回の展覧会について語るべきことは、以上に尽きているのかもしれない。しかしながら、2007年以来、四度にわたって継続されてきているこの企画展シリーズの蓄積を考えると、さらにここで確認しておくべきことがあるのではないかと思われる。
「記憶の位相」(2007年)、「Invisible moment」(2008年)、「Land Site Moment Element」(2009年)、そして今回の「ながめる、まなざす」。これらのタイトルはいずれも、風景と写真をめぐる仕事の現在形という大枠のもとに、参加した写真家たち自身がグループ展を成立させるための対話のなかでつむぎだしたものだという。試みに、ここまでの議論に則して考えてみると、これまでの三回のタイトルは、外界や内面、あるいは参照される問題系をめぐって選ばれた言葉であると解釈できる。それに対して今回の「ながめる、まなざす」というタイトルは、「風景」が立ち上がるプロセスにおける写真家の視覚のモードについて記述する言葉である。そして展覧会のコンセプトが固められていく過程で、「拡張する眺め、まなざしの収束」というタイトル案があがったという。ここには「拡張」と「収束」という互いに逆方向のベクトルをもつ運動性が浮上している。最終案では省略された、この視覚の二つのモードがはらむ逆方向の運動性にこそ、風景をめぐる写真家の営みが直面する今日的な課題をとらえる手がかりがあるように思う。
風景と写真をめぐるこの企画展シリーズの背景には、私たちをとりまく世界がデジタル・テクノロジーの浸透によって変容し、写真メディア自体もデジタル化によって急速に変化しているという状況があった。現実の空間をグローバルな情報のネットワークが覆っていることが、日常的に実感されるような状況において、写真というメディアを介して、リアルであれヴァーチャルであれ、私たちをとりまく状況に「風景」を立ち上がらせること。今回のタイトルは、そうした試みをめぐって「身体性」というキーワードが浮上してきたことを示唆しているのではないだろうか。
ネットワークに浸透された日常において、私たちの経験は、ある意味で身体という枠を超えて限りなく拡張されている。しかしそうした経験を重ねれば重ねるほど、結局のところ、私たちの生が身体に限界づけられていることが、なかば無意識のうちに自覚されてきているのではないか。「ながめる、まなざす」という視覚の二つのモードが示唆する逆方向の運動性、絶えず反転しながら振動するような運動性とは、そうした私たちを限界づけている生身の身体の本質である。そしてその運動性こそが、デジタル情報のネットワークの網の目からこぼれ落ちる微細なノイズを感知し、そこからかすかなシグナルをすくいあげることを可能にするだろう。実は写真というテクノロジーは、その局面で、必ずしもデジタル・ネットワークに親和的にふるまうわけでなく、むしろ生身の身体の側に位置しているのではないか。
今回の展覧会は、そうした風景をめぐる写真メディアの今日的可能性を見究めようとする、写真家たちの現状報告なのである。